
Part1はTOEIC試験で最初に解くPartです。Part1で安定して解ける力を身につければ、その後の試験を良いリズムで進められます。
ということでこのページでは、Part1の正答率を高いレベルで安定させるための攻略法を解説します。
しかも、今後解説する他のPartの攻略法と比べて、今回解説するPart1の攻略法は簡単かつ即効性があります。
なので、特にPart1が苦手な方はぜひ参考にしてください!
①単語帳でPart1単語を覚える
まずやって欲しいのは単語帳を使ってPart1の単語を覚えることです。
Part1に出てくる単語の種類は、それほど多くありません。よって、単語を一定数覚えるだけで、Part1は驚くほど解きやすくなります。
ではどんな単語帳を使うべきかというと、定番の「銀のフレーズ」「金のフレーズ」でOKです。
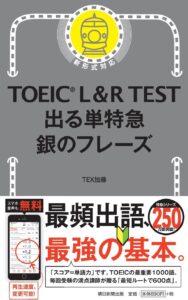
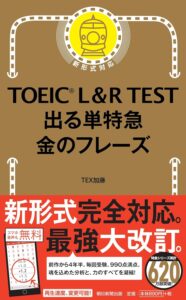
知らない方が非常に多いんですが
- 銀のフレーズには「パート1重要語50」
- 金のフレーズには「パート1重要語100」
という補足英単語集が載っています。
ちなみにLINE追加特典の「TOEICパート1英単語集」にも「銀フレ金フレ+α」でまとめているので、そちらを使っていただいてもOKですよ。
②問題を解く
Part1重要語を覚えたあとは、実際に問題を解きましょう。
頭の中では「覚えられた!」と思った場合でも、実際に問題を解くと意外と単語の意味を思い出せないことが多くあります。
よって、問題を解いて形式に慣れつつ、「単語の引き出し力」を鍛えていきましょう。
なお、使用する問題集は「公式問題集」がおすすめです。
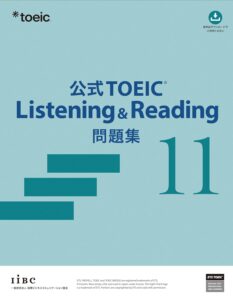
また、基本的には公式問題集だけでも十分ですが、さらに問題演習量を増やしたい場合はPart1特化の参考書を使いましょう。
おすすめの参考書は「パート1・2特急 難化対策ドリル」です。
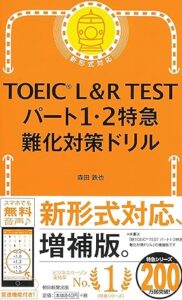
税込924円と価格がリーズナブルな割に、Part1の問題を50問掲載しています。ちなみにPart2の問題も150問載っています。
「難化」とついているので手が出しづらく感じるかもしれません。ただ、最近のTOEIC本番の難化傾向を考えると、むしろちょうど良いレベルだと個人的には思います。
また、リスニングが苦手な方やTOEICスコアが概ね400点未満の方は「公式問題集」や「パート1・2特急 難化対策ドリル」だと難しく感じる可能性があります。
よって、「初心者特急パート1・2」を使うのがおすすめです。
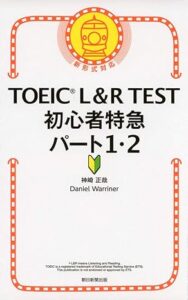
③問題演習後はわからない英単語を覚える
「公式問題集」や「パート1・2特急 難化対策ドリル」で演習した後は、問題に登場したわからない英単語を地道に覚えましょう。
これをやるのとやらないのとでは、Part1の安定力が大きく変わってきます。
④ディクテーション
ディクテーションというのは、聞き取った音声を書きとる練習方法です。
- 聞き取りの集中力が身につく
- 正しい発音がわかる
- 自分が聞き取れない箇所が明確になる
といった効果があります。特に大きいのは③で、自分が聞き取れない箇所を聞き取れるようになるまで聞き直せば、リスニング力は効率的かつ着実に向上します。
ディクテーションの具体的なやり方は以下の通りです。
- 音声を1度聞いて大まかな内容を把握する
- 1回1回音声を止めながら書き取る
- 繰り返し再生して「もう無理」というところまで書き取ったら次の文に
- スクリプトと書き取りを照らし合わせる
- 「書き取りが間違ってた部分」「書き取れなかった部分」は聞き取れるようになるまで聞き直す
- 慣れてきたら音声のスピードを速くする
基本的にはここまで解説したように
- 単語帳でPart1を覚える
- 問題を解く
- 演習後にわからない英単語を覚える
でもPart1はかなり解けるようになります。
⑤写真の状況を自分で説明する

問題集の写真を使って(もしくは上記のような写真を自分で用意して)、写真の状況を自分で説明してみるという練習方法もあります。
たとえば上の写真なら
- A person is riding a motorcycle across the street.
- Cars are parked along the sidewalk
- A woman is running
みたいな感じです。
この練習を行うことで、写真の細部にまで注目する力が身につきます。
Part1を解くコツ
ここからはPart1を解く楽にコツを解説します。
ここまでの勉強法と合わせて、これから解説するコツを実践すれば、Part1がさらに解きやすくなるのでぜひ参考にしてください!
①現在進行形の受け身にはとことん注意する
Part1では、”The furniture is being installed”というように、現在進行形の受け身が含まれる選択肢がよく登場します。
実は、現在進行形の受け身が出てきたら、その選択肢は引っ掛けである可能性が高いです。(100%ではありません。)
というのは、たとえば”The furniture is being installed”は「家具がまさに今設置されているところだ」という場面を表しています。
つまり、設置している人物が必要なんですね。
もし写真の状況を適切に描写するとしたら、現在形や現在完了形の受け身が使われます。
たとえば、The furniture has been installed.という感じですね。これであれば正解となります。
②写真の細部にまで徹底的に目を通す
人間の心理的にしょうがないのかもしれませんが、写真を見た時、どうしても中央に写っている人物やモノばかりに注目しがちです。
もちろん中央に写っている人物やモノに注目するのは大切なんですが、写真の端っこの方に写っている人物やモノに関する選択肢が正解になることもあるんです。
もし事前に写真の端っこの情報まで確認していなければ、問題で端っこの部分に関する選択肢が読まれた時に対応できなくなります。
よって、問題を解くときは、「奥にハシゴがある」とか「左側にバイクに乗った人がいる」というように、しっかり写真の細部まで確認することを徹底しましょう。
リスニングではそれぞれのPartが始まる前に、問題の内容や形式を説明するdirectionが流れます。
このdirectionは聞かなくても問題を解けるので、directionが流れている間にPart1の問題6問の写真にしっかり目を通しておきましょう。
③似た発音に注意する
- box:books
- grass:glasses
- copy:coffee
- car:cart
というように、似た発音の単語はよくあります。
写真の中にboxが写っているとします。そして選択肢の中で「books」を含んでいるモノがあるとします。
このような場合、”box”と”books”の発音が似ているので、ついつい”box”と勘違いして”books”が含まれる選択肢を選んでしまうことがあります。
しかし、それはNGです。選択肢を検討するときは単語単体ではなく、必ず前後の英文までチェックしてください。
たとえば、選択肢が”The man is reading books”だとしましょう。
この場合、もしboxとbooksを聞き分けられなかったとしても、「reading」が聞き取れていれば、その選択肢は間違いだと判断できます。
④語句の言い換えに注意する
- desk(机)→furniture(家具)
- bus(バス)→vehicle(乗り物)
- piano(ピアノ)→instrument(器具)
- book(本)→merchandise(商品)
- cat(猫)→animal(動物)
というように、写真の中に写っているモノが、より抽象的な語句に言い換えられて選択肢に含まれ、それが正解になる場合があります。
このルールを知らないと、「どの選択肢も間違っている!」と混乱する可能性があるので、しっかりおさえておきましょう。